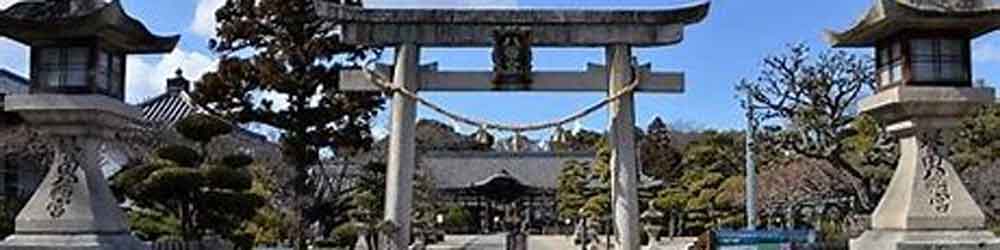
その他の省略項目
随神門、中雀門、宝物殿、社務所(授与所)、百度石、注連柱、標柱、注連縄祠、摂社、末社鈴、ご神木、石神さま、のぼり、旗石碑、記念碑、紀念碑、おみくじ結び処、掲示板、案内板、撫牛(撫で牛)、絵馬、絵馬掛所、千本鳥居、明治天皇聖躅銅像、石像、道祖神、神馬、梅の木、十二支方位盤、看板、国歌、国旗献灯台、提灯
一寸、音楽でも聴きましょうか・・・ "Ojos negros"(黒い瞳)
随神門、中雀門、宝物殿、社務所(授与所)、百度石、注連柱、標柱、注連縄祠、摂社、末社鈴、ご神木、石神さま、のぼり、旗石碑、記念碑、紀念碑、おみくじ結び処、掲示板、案内板、撫牛(撫で牛)、絵馬、絵馬掛所、千本鳥居、明治天皇聖躅銅像、石像、道祖神、神馬、梅の木、十二支方位盤、看板、国歌、国旗献灯台、提灯
一寸、音楽でも聴きましょうか・・・ "Ojos negros"(黒い瞳)
このページは、html勉強用に作成したものです。
写真は「ぱくたそ」、文章は「ウィキペディア」から利用しています。
社務所
神社で行う 事務 一般を称して社務といい,それを執行する建物を 社務所 と呼ぶ。

鎌倉宮の社務所
また 往古、 神職 の長として一社の事務を執行したものを社務あるいは 社務職 (しやむ しき )ともいった。 松尾神社 , 平野神社 , 住吉神社 , 鶴岡八幡宮 などの諸社には,これが置かれた。
社務の語が一般化したのは明治以降で, 神社 が 国家 の管理下におかれたため, 公務 を行う事務所が必要とされ,多くの神社に社務所が作られた。

東山-秋葉社-社務所
社務所は神社の付属施設として境内に設けられている。ここは神職や巫女(みこ)が待機する場所であり、また神社や祭神についての案内を行い、祈祷(きとう)を受け付ける。社頭は開かれており、神札(しんさつ)や守札(まもりふだ)、破魔矢・絵馬・おみくじなどを授与している。
ただし、これらのものを購入するのは、買うと言わず、受けるという。これは商品ではなく、信仰の対象であるがゆえである。

日光-二荒山神社-社務所
なお「神札」とは神社の祭神が分霊し依り坐す最も重要な札。自宅へ持ち帰り、神棚に納めるもの。伊勢神宮のものはとくに「大麻札(たいまふだ)」と呼称する。
|
|
「守札」は携帯用の神札で、肌身に着けて常に持ち歩く。
「破魔矢」は文字通り魔を破る矢で、家の中の目立つところに置いて魔除けとする。
「絵馬」は裏側に願い事を書いて、神社のしかるべき場所に掲示し、神に奉る。
「おみくじ」は吉凶の占いで、日々の指針とする。
Copyright(C) 2021- [Chick in Osaka] All Rights Reserved.

