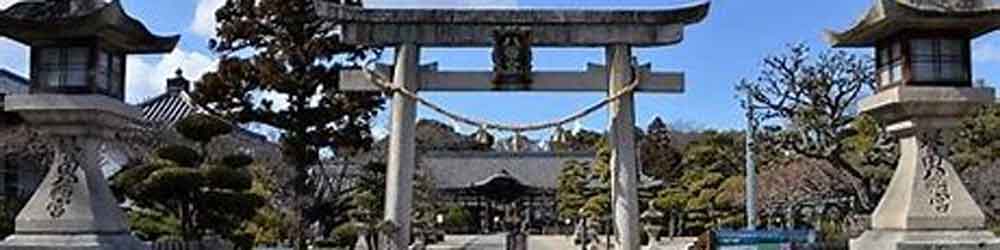
一寸、一息、
このページは、html勉強用に作成したものです。
写真は「ぱくたそ」、文章は「ウィキペディア」から利用しています。
神社
神社(じんじゃ・かむやしろ)とは、日本固有の宗教である神道の信仰に基づく祭祀施設。産土神、天神地祇、皇室や氏族の祖神、偉人や義士などの霊などが神として祀られる。
文部科学省の資料では、日本全国に約8万5千の神社がある。登録されていない数万の小神社を含めると、日本各地には10万社を超える神社が存在している。
|
|
神社は日本固有の宗教である神道の祭祀施設であるとされているが、その位置付けは時の政治の状況との関連もあり一定していない。律令国家においては式内社が国家による祭祀の対象として神祇官の統制下に置かれたが、その頃から既に式外社と呼ばれる神祇官の統制外にある神社もあったことは確実である。
神祇官(じんぎかん、かみづかさ、かんづかさ)とは、古代の日本の律令制で設けられた、朝廷の祭祀を司る官位名。平安時代の中ごろ、西暦927年に朝廷では神社や宮廷の祭祀について律令(ルール)が作られた。それが「延喜式」であり、朝廷が特に重要と認めた神社を「官社」に指定して全3132座(2861所)をリストアップした。それが延喜式内社である。

新宮・熊野古道の神倉神社
近世においては仏教の施設となった神社や修験道・陰陽道の影響下にある神社も存在していたが、一方で伯家神道や吉田神道と言った他宗教からは独立した神道の神社もあった。近代になると神社は国家神道として神道系の宗教を含むあらゆる宗教から建前上は分離されたが、その位置づけには議論があった。宗教としての神道は教派神道として神社と分離された。
現代においては国家神道は廃止され、多くの神社は神社神道に分類される宗教団体の施設として再編された。その多くは神社本庁に所属している。

貴船神社奥宮
現代においても神社の在り方はさまざまである。有名な神社であっても、難波神社・鎌倉宮・靖国神社・伏見稲荷大社・日光東照宮・気多大社・梨木神社・新熊野神社・富岡八幡宮など神社本庁との被包括関係を有せず、単立宗教法人として運営される場合がある。
大きな単立神社は約2000社、宗教法人格を有さない小さな祠等を含めると20万社の単立神社がある。

上賀茂神社
東大阪市のように宗教法人格を有している神社に限っても半数以上が神社本庁に属していない地域もある。さらに神社本庁以外にも神社神道系の包括宗教法人がいくつかあり(神社本教、北海道神社協会、神社産土教、日本神宮本庁など)、これに属する神社は神社本庁の被包括関係には属さない。
また、教派神道や修験道、陰陽道、神道系新宗教(大和教団、大倭教等)や保守系の諸教(生長の家、天照皇大神宮教等)に所属している神社も存在している。
一寸、一息、
Copyright(C) 2021- [Chick in Osaka] All Rights Reserved.

