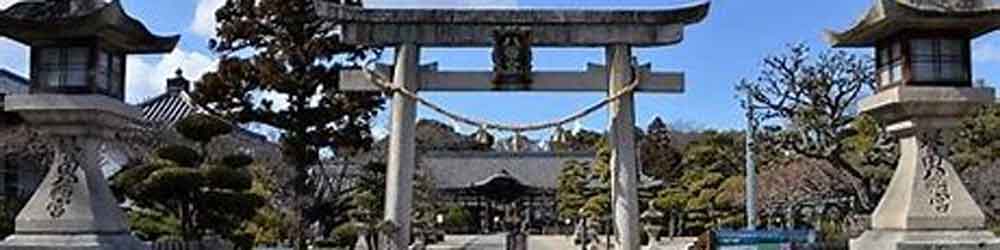
随神門、中雀門、宝物殿、社務所(授与所)、百度石、注連柱、標柱、注連縄祠、摂社、末社鈴、ご神木、石神さま、のぼり、旗石碑、記念碑、紀念碑、おみくじ結び処、掲示板、案内板、撫牛(撫で牛)、絵馬、絵馬掛所、千本鳥居、明治天皇聖躅銅像、石像、道祖神、神馬、梅の木、十二支方位盤、看板、国歌、国旗献灯台、提灯
一寸、音楽でも聴きましょうか・・・ "川は流れる"
このページは、html勉強用に作成したものです。
写真は「ぱくたそ」、文章は「ウィキペディア」から利用しています。
神楽殿
神楽(かぐら)は、日本の神道の神事において神に奉納するため奏される歌舞。
神社の祭礼などで見受けられ、まれに寺院でも行われる。平安中期に様式が完成したとされ、約90首の神楽歌が存在する。神楽は、神社に「神楽殿」がある場合、そこで行われる事が多い。

出雲大社の神楽殿
一般に、「かぐら」の語源は「神座」(かむくら・かみくら)が転じたとされる。神座は「神の宿るところ」「招魂・鎮魂を行う場所」を意味し、神座に神々を降ろし、巫・巫女が人々の穢れを祓ったり、神懸かりして人々と交流するなど神人一体の宴の場であり、そこでの歌舞が神楽と呼ばれるようになったとされる。
古事記・日本書紀の岩戸隠れの段でアメノウズメが神懸りして舞った舞いが神楽の起源とされる。アメノウズメの子孫とされる猿女君が宮中で鎮魂の儀に関わるため、本来神楽は招魂・鎮魂・魂振に伴う神遊びだったとも考えられる。
|
|
神楽は、宮中の御神楽(みかぐら)と、民間の里神楽(さとかぐら)に分けられる。また幾つかの神社では、近代に作られた神楽も行われている。

氷川神社の神楽殿
神楽を舞うための施設を神楽殿(神楽堂、楽殿)という。[2][3] 舞楽専用の施設を舞殿として区別することがある。[4] 特に里神楽では様々な用途の舞台(演舞場、演武場、音楽堂)、ライブステージ、コンサート会場として利用されることもある。

日光東照宮の神楽殿
宮中の賢所で行われる御神楽(賢所御神楽)は、古くは内侍所御神楽と言われた。雅楽(国風歌舞)に含まれる。
大嘗祭の清暑堂での琴歌神宴(神楽)、賀茂臨時祭の還立の神楽、園并韓神祭の神楽、石清水八幡宮臨時祭の神楽がもとになったという。一般的に「神楽」と言われるものは里神楽で、御神楽と対比して用いられ、狭義では関東の民間の神楽を指す。
Copyright(C) 2021- [Chick in Osaka] All Rights Reserved.

